HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第229回 「電子政府エストニア、その3『なぜ130万人の国がユニコーン企業を次々と輩出できるのか?』」

2019/10/07
10月「神無月」、8日は24節気の「寒露」です。“草木に冷たい露が降りる頃という意味です。秋の長雨が終わり、ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他の農作物の収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きはじめます。”と言われてます。
(暮らしの歳時記 http://www.i-nekko.jp/meguritokoyomi/nijyushisekki/index.html)
(前回より)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〇電子政府エストニアの成功要因
以下forbesjapanより抜粋・編集
https://forbesjapan.com/articles/detail/19386
・エストニアの「電子政府」の成功要因は大きく3つに分けられる。
一つ目は歴史的背景
二つ目は地理的要因
三つ目は政府の推進方針
1.歴史的背景
・ソ連が残した唯一の遺産を活用
中核をなす情報基盤連携システムの「X-ROAD」
領土を必要としない国家の構想 ー> 「データ大使館」
たとえ国が侵略されて物理的に「領土」がなくなったとしても、国民の「データ」さえあれば国家は再生できる
2.地理的要因
・隣国フィンランドからの教訓
「IDカードの所持は義務とするべきだ」
3.政府の推進方針
・電子政府への信頼は透明性から
「効率」と「透明性」であり、透明性以外に電子政府の信頼を構築していく術はない。
データのマネジメントとガバナンスを、法制度として確立
行政による徹底した情報開示の姿勢をとっており、透明性が担保されている
公共情報法(Public Information Act)
個人データ保護法(Personal Data Protection Act)
電子署名法(Digital Signature Act)などが施行
・プライバシー保護「6つの原則」
1.分散化
2.透明性
3.ワンスオンリー
4.ノー・レガシー
(公的部門は13年以上古いツールは使ってはならぬ。)
5.ユーザーフレンドリー
6.データの完全性(KSIブロックチェーン技術)
同国の人々は政府の人間を信頼しているのではなく、政府の仕組みを信頼しているのだ。不正があったとしてもきちんと検知できる仕組みがあれば、国民が納得して電子政府を受け入れることができる。
以下からは、「つまらなくない未来(孫泰蔵監修、小島健志著)」より抜粋・編集
〇エストニアとは
・未来社会の道しるべ
ヒューマン・オートノミー(自由)への社会
・行政サービスの99%が年中無休で利用できる国(e-Estonia)
eIDカード ー> 本人確認と電子署名
X-Road(情報交換基盤システム)ー> ブロックチェーン
e-Residency(仮想居住者)
・国の提供する「OS」の上に様々な「アプリ」が誕生
Jobbatical(グローバル人材サービス)
・仮想住民を巻き込んだ新たな社会が生まれる
国全体が「グローバルバックオフィス機能」を提供
「デジタルノマド」、「デジタルノマドビザ」の発行
仮想通貨「エストコイン(ブロックチェーン技術)」
、ICO(トークンを利用した資金調達)
契約のあり方を変える「スマートコントラクト」
〇デジタル政策年表
年 出来事 内容
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1991 独立回復 旧ソ連からの独立
1996 e-バンキング キャッシュレス文化浸透
タイガーリープ 全校へインターネットとコンピュータ設置
2000 e-タックス 電子税申告システム稼働
e-キャビネット 閣議の電子化、電子署名法の制定
2001 X-Road エックスロードの運用開始
2002 eIDカード デジタルIDカードの配布開始
e-スクール 学校の情報を共有できる仕組み
2005 アイボーティング インターネット投票
2008 e-ヘルス 電子医療システム稼働
2012 プログラミングタイガー プログラミング授業開始
2014 e-レジデンシー 仮想居住制度の開始
2019 デジタルノマドビザ 仮想住民へ1年間滞在ビザ発給予定
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎電子政府エストニア、
その2『なぜ「何もない国」がIT先進国に変われたのか?』」
<ICTキーワード *>
1.「はんこ」も「書類」もない国で
*電子署名
2.電子政府エストニアの正体
・生まれてたった10分で、国民ID番号を付与
・行政手続きの99%をオンライン、24時間365日
・なりすましは不可能、電子身分証(eID)、普及率は98%
・オンライン上で完結できない3つのこと
1.結婚
2.離婚
3.不動産の売却
3.なぜ何もないのに電子化が実現できたのか
・1991年
社会主義 −> 資本主義 へ移行
・2001年
* X-Road(分散型のデータ交換基盤システム)
・2004年
NATO、EUへ加盟
4.どのようにプライバシーを守るのか
・「政府は信用していないけど、制度は信用している」
1.透明性
情報のコントロールを個人に!
2.ワンスオンリー
情報公開法:
同じデータを集める目的で、複数データベースを構築することを禁じている。
・6つの原則
1.分散化
2.透明性
3.ワンスオンリー
4.ノー・レガシー(公的部門は13年以上古いツールは使ってはならぬ。)
5.ユーザーフレンドリー
6.データの完全性(*「KSIブロックチェーン」技術)
5.「ブロックチェーン国家」と呼ばれる理由
・2007年のサイバー攻撃
−> データの完全性
・2011年(ガードタイム(2007年設立)社提供)
* ブロックチェーン導入(「KSIブロックチェーン」)
−> 「1秒ごとにデータの完全性を証明」 ・・・ タイムスタンプ
6.データとは誰のものなのか
・GDPR(一般データ保護規則)(2018年5月25日施行)
・データ個人主権
7.テクノロジーを使いこなし自由に生きる
・日本との比較
「日本のマイナンバー制度」は、マイナンバーではなく“ユアナンバー”!?
ナンバーカードの取得は任意
利便性の実感がない
データのコントロール権は国家
公文書の改ざん問題 改ざんできる仕組みが残る
セキュリテリー面での信頼性が担保されていない
〇なぜ世界中のトップ人材はいまエストニアを目指すのか?
・世界で初めて「国境のない国」になる
エストニアの取り組みは、国内の手続きに止まらない。同国は、2014年には「 e-Residency」という制度を開始した。国民IDカードを、居住権を持たない外国人にも発行して、エストニアの公的プラットフォームを利用できるようにするサービスである。このサービスを利用すれば日本人が日本にいながらにしてエストニアにオンラインで会社の登記が可能になる。まさに「Government as a Service」である。
1.4万人を超える“仮想住民”の誕生
・仮想住民を生む「イーレジデンシー」 2014年〜
・3つのメリット
1.電子政府が体験できる
2.電子署名が使える
3.オンラインで法人設立ができる
・デジタルノマド≒グローバルフリーランサーをターゲット
2.世界のトップ人材を呼び込む「秘策」
・1億人のグローバルフリーランサーを狙い1年間有効の新ビザを創る
・「ジョバティカル(求人サイトサービス)」 2019年〜
・「デジタルノマドビザ」で拓ける旅をしながら働くという可能性 2019年〜
・仮想通貨「エストコイン」他、新たなサービス
テレポート、リープイン、ファンダービーム/ICO(資金調達)
3.土地に縛られない生き方から見える可能性
・安全保障面からみた仮想住民の秘めたる力
データさえ守れば怖くない、領土すら捨てる覚悟
ノマド戦略 ≒ ユダヤ人
−> *「データ大使館」(ルクセンブルグのデータセンター)
4.グローバルフリーランサーという新しい働き方に目覚める
・エストニアの5つの魅力
1.デジタル社会
2.自然の豊かさ
3.オープンマインド
4.ワークライフバランス
5.多様性
・日本との比較
「日本のマイナンバー制度」は、マイナンバーではなく“ユアナンバー”!?
ナンバーカードの取得は任意
利便性の実感がない
データのコントロール権は国家
公文書の改ざん問題 改ざんできる仕組みが残る
セキュリテリー面での信頼性が担保されていない
などなど
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(以上)
〇なぜ130万人の国がユニコーン企業を次々と輩出できるのか?
・世界初の政府主導ICO(Initial Coin Offering、自らのトークンやコインを発行して資金調達を行うこと)
バーチャル住民に向けて「Estcoin」を発行する構想を発表した。
1.スカイプを生んだ国、スカイプを生んだエコシステム
・国立博物館の「英雄」のイス
(スカイプ誕生の地、エストニアの技術者の象徴)
・P2P技術 2001年 2002年に売却
スカイプの開発 2003年 米イーベイが買収(2800億円)
100人以上のエストニア人技術者がIT産業の礎を築く
「小さい国からも世界に通用するサービスを生み出すことができるんだ!」
・スカイプマフィア
P2P、ブロックチェーン技術を基礎とした「分散型」
*スタートアップ累計調達額トップ10+α
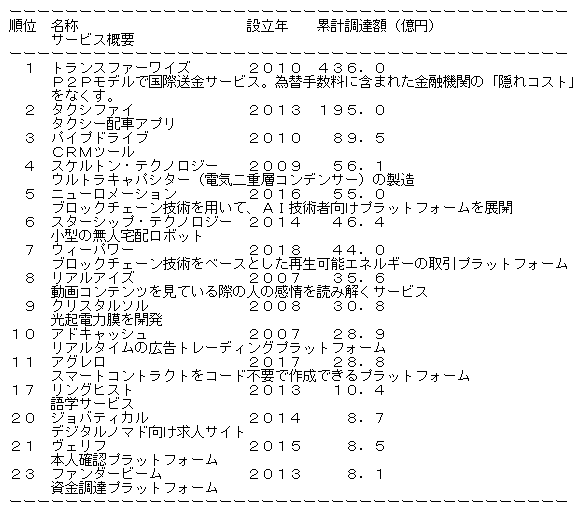
2.次のスカイプを狙う「エストニアン・マフィア」とは何者か
・「LIFT99」 コミュニティ
・起業家によるコミュニティ運営が新興企業の成長を促す
・スカイプ出身者が投資家としての役目を担う
・投資家の存在があってこそ急成長
循環する仕組みを「エコシステム(生態系)」
3.ユニコーン企業を生み出すエコシステムの秘密
・エンジェル投資家の存在が海外からの資金を引き出す
・起業家マインドは先進国でトップレベル
・スマートコントラクトで契約革命を起こす
4.「トークン・エコノミー」の産声
・「経済実験」を行う日本人起業家
ブロックハイブ社CEOの日下光氏
・ソーシャルキャピタル
・ICO −> 「ILP」(貸付型の資金調達)
5.エコシステムが生まれ、挑戦する人があふれ出す
・エコシステム構築に欠かせない5つの視点
1.起業家によるコミュニティの形成
2.起業家マインド育成とセーフティネット
3.規制当局とスタートアップの交流
4.いきなりグローバルを目指す企業のネットワーク化
5.エコシステムのブランディング化
組織に属する人間だとしても、個人の信用というものを意識せざるをえない時代を迎えている。学歴や職歴、出自といた内容にとどまらず、それまで行ってきた仕事や活動が記録され蓄積されてゆく。これはあらゆる業界業種に及ぶだろう。意識すべきは、個人としての信用をいかに築いてゆくかと思われる。
この生態系に生息する者は、会社形態というよりプロジェクトチーム型で仕事が進んでゆくことになる。必用なものは、個人としての信用である。
令和元年10月03日