HOME > 公共分野 > 自治体分野 > 導入事例 > 大阪府八尾市

![]()
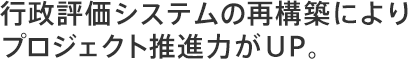
![]()
![]()
大阪府中河内地域に位置する八尾市。同市ではめざす将来都市像を実現するために、全庁的に行政経営を進めるうえでの効率的なツールとして「行政評価システム」を再構築しました。
計画の進捗が可視化され、情報公開も迅速に対応できるようになりました。
目標計画を基本に1つのシステムで確認することができるので、効率的な行政マネジメントに結びつきプロジェクト推進力がアップしました。
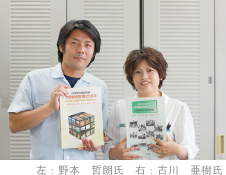
平成23年(2011年)、八尾市ではめざす将来都市像を明らかにし、その将来都市像を実現するための方向性を示す第5次総合計画「やお総合計画2020」を策定しました。この総合計画を推進するにあたり、総合計画の政策体系に沿った形で行政評価に取り組めるよう、行政評価システムを再構築しました。
八尾市では、平成23年4月から今後の10年間のまちづくりの指針となる「やお総合計画2020」に基づき市政の運営を行っています。この総合計画は、庁内における議論だけでなく、市民の皆様とともに知恵を出し合い協働しながら策定したもので、基本構想と基本計画から構成されています。

平成13年に策定した第4次総合計画より、本格的に行政評価への取り組みを開始しました。当初は表計算ソフトを駆使し、手入力による事務事業評価を行っていましたが、17年度の事後評価より行政経営支援システムを導入しました。
以前利用していたシステムは、行政評価に様々な観点を加え、豊富な機能が盛り込まれたものでしたが、必ずしも使いこなしきれない所もあったため、今回は総合計画を推進するうえで必要な機能に絞り込み、シンプルで使いやすいシステムをめざしました。
また、旧システムは、どちらかと言えば、事務事業評価の中で改善点を洗い出す機能を充実したため、事後評価を行い、公表することに力点を置いた運用となっていました。そのため、今回必要な機能を整理したところ、新たな機能追加も必要でした。
主に3つの機能が必要だと考えました。1つは、今回の総合計画の特徴でもある地域別計画を推進するため、「地域」の観点を持って、事前・事後評価を行える機能です。
2つ目は、ローカルマニフェストの実現に向け、まずはマニフェスト実行計画として行政計画化し、総合計画と一体的に推進する機能が必要と考えました。これまでは、システムと別立てで表計算ソフトを使い、非効率でした。
最後は、行財政改革アクションプログラムの推進を、事務事業評価の流れに組み込み、一体運用する機能であり、行革項目を事務事業評価に位置づけ、システムで共有することが必要でした。
第5次総合計画は、各施策に明確な数値目標として成果指標を設定しており、それを順次達成していくには、戦略的な行政経営を行う必要があります。そこで、部局という組織軸で戦略目標を共有化し、そのパーツを部内所属が受け持ち、個人の目標として頑張った結果が、施策実現となる仕組みを構築することで実効性を高めました。また、次年度の組織目標が予算編成に直結する流れとすることがポイントでした。これを、「部局マネジメント目標」を主体とする行政経営として仕組みづくりを行い、行政評価は戦略を立てるための基礎データ集約と位置づけたうえで、システムの機能を整理し、評価業務の効率化も実現しました。また、事務事業の方向性が確定した後、それに基づき予算編成が行われる流れも定着しました。
「部局マネジメント目標」の取り組みで、次年度の部局戦略を立て、それを受けてシステムで「事前評価」を行う運用としたことは、重要なポイントの1つです。合わせて、施策や事務事業の予算や人的リソースの配分も、入力作業の中での見える化だけではなく、財務会計システムと連携を行い、3月議会で当初予算案参考資料となる事前評価帳票にも、方向性と事業費の双方を掲載する機能を採り入れることで、評価の方向性と軌を一にした予算配分の最適化が進みました。
すべての事務事業評価の中で、事業の位置づけそのものを根本的に問い直す評価観点を、機能として組み入れました。まず、事前評価の中に、広域連携をすべきかという項目を設け、市の事業として取り組むべきか、広域連携で行うべきか、位置づけを問う評価から始めています。また、同様に、市民との協働で事業に取り組むべきか、どのレベルで協働すべきか考える項目も採り入れています。さらに、事後評価の中でも、八尾市版の事業仕分けとして、事務事業分類のふるいにかけ、民間で同様の事業がないか、市で本当にやるべきか、公民協働手法を導入すべきか、問い直す評価を採用しました。
総合計画を実現するために、戦略的かつ実効性のある行政経営の仕組みを構築するうえでは、学識経験者である行政経営アドバイザーに相談しながら、市の実務担当者としての思いや疑問を聞いていただき、じっくりと時間をかけて「部局マネジメント目標」を主体とする仕組みを定着させ、その全体の仕組みの中で、「行政評価」に求める機能や、評価項目を検討しました。
また、人口減少社会で、持続可能な行政経営を進めるためには、中期の財政計画のもと、ビルドとスクラップが整合性を持って機能することが必要であり、企画担当課と行革担当課が、ともに必要な機能を整理し、システム構築を進めてきました。
職員であればだれでも、庁舎内約1,000台のPCからWebブラウザを通じてシステムへアクセスでき、管理者メニューを除くすべての項目を閲覧できるようになっています。
入力に関しては、施策については施策担当課が、事務事業については担当課が入力できるようになっており、63の施策に関しては課長が、約760の事務事業に関しては実施計画の策定担当者、主に係長が、事前・事後評価を入力する運用としています。
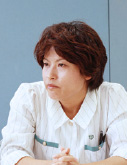
目標別計画を基本に、地域別計画、行財政改革アクションプログラム、マニフェスト実行計画といった市の重要計画と、各事務事業の関連性を1つのシステムの中で確認しながら見ることができるので、年間の事業サイクルに対する共通認識が高まり、効率的な行政マネジメントに結びついています。
また、部局長や所属長だけでなく、現場の職員も、自分自身が関わっている事務事業や業務がどの計画や施策に結びついているのかが明確に見えるようになりました。これらの情報は組織目標や個人目標とも連携しているので、各計画が形だけではなく具体的に業務とどう連動しているのか、関連性や重要性についても理解してもらいやすくなったと思います。
一方、すべての計画や業務に関しても同じレベルの情報が閲覧できるようになったので、普段は知ることが難しい他部署の業務や市としての動き、スケール感、スケジュール感なども実感してもらえるようになったと考えています。
以前は、決算審査特別委員会などに提出する資料をまとめる際、政策体系ごとに各事務事業情報を収集しなければなりませんでした。しかし、新しい行政評価システムでは、あらかじめ施策単位で事務事業の指標等必要な項目を設定した帳票を用意し、簡単に出力できるようになりました。
また、各計画や業務の進行状況に対する突発的な問い合わせに対しても、迅速かつ効率的に対応できるようになりました。
行政評価システムの役割は、施策・事務事業を評価するだけではなく、総合計画を実現するうえでの支援ツールとなることです。どのシステムも同じかもしれませんが、ツールの導入が目的ではありませんので、個々の職員が全体の仕組みを理解し、担当業務の位置づけを把握したうえで、「施策」と「地域」の両観点を持った立案ができるように、ツールを使いこなせるよう共通認識を高めることが、今後の課題だと考えています。
また、機能面では財務会計システムとの連携を強化していければと考えています。
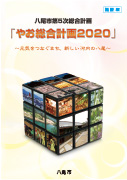
![]()
大阪府中河内地域に位置する特例市。西は大阪市に、北は東大阪市に、南は柏原市・松原市・藤井寺市に、東は生駒山系を境にして奈良県に接している。平成20年4月には市制施行60周年を迎えた。
取材日:2012年9月
※文中に記載されている数値など情報は、いずれも取材時点のものです。