明治学院大学 横浜校舎図書館
本から人へ、人から人へ。 思わぬ“出会い”を生む。

図書館を、大学生活の中心にするための挑戦。
明治学院大学の横浜キャンパス。広大なキャンパスの中心に位置するのが、2015年春にリニューアルされたばかりの図書館です。授業やゼミ、サークル活動などを大学生活の中心に据える学生が多いなか「図書館を中心に、さまざまな体験をしてほしい」「そのためには、どんな図書館が最適なのか?」と議論を重ねた結果、完成した空間です。ラーニング・コモンズ、アクティブ・ラーニングなど、学生たちが主体的に学べる機能を多様に備えながらも、「本に触れる経験も大切にしてほしい」と秋月図書館長。その象徴ともいえるのが、入り口に据えられた高い書架。“本の世界に圧倒される”ということが、視覚からダイレクトに伝わってきます。
「いまの学生たちは、ひとりではなく自分たちで何かを得ようとすることは得意。それを図書館でも生かしてほしい。 パソコンやホワイトボードを使って、ひとりの考えをみんなで共有することもひとつの方法です。学生がその刺激によって成長したり、変わっていくなかで、講義に改革がおこったり、横浜キャンパスの図書館での動きが白金キャンパスにも伝わるといいなと思っています」(秋月館長)。
 |
ラーニング・コモンズ、アクティブ・ラーニングの考えを取り入れ、学生たちが主体的に学ぶための場「アクティブコモンズ」を設置。学生たちが互いに刺激し合いながら学べるよう、可変的でオープンな空間。
 |
「メインホール」に置かれた存在感のある書架。日常では本に触れる機会が少ない学生たちも、別世界に誘われるようなワクワク感が味わえる。
 |
オープンな空間、ガラス張りの空間など、学生同士が意識しなくとも互いの活動を感じ取ることで、刺激し合える。
 |
軽飲食OK、カフェのような「りぶら」。雑誌や新聞などもそろえて、毎日気軽に学生たちが立ち寄れるような雰囲気づくりもされている。
 |
本との思わぬ出会いが期待できる「ブックスケープ」。“本の森”“本の迷路”をイメージして、360度、取り囲むように書架が配置されている。
 |
本についたバーコードと連携。本をかざすと画面に関連書籍が表示される、BOOKコンシェル「オススメくん」。
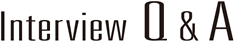

- 学生たちに、期待することは?

- 新しい図書館で学生たちに知ってほしいのは、「本に触れることによって“何らかの目的が達成できる”という実感」です。興味のあるものだけに一直線に行くのではなく、幅広い世界に触れるのも重要なこと。学生の本離れが言われることもありますが、昔に比べて本に触れる場そのものが日常では減っていますし、出版物の質も問題なのかもしれません。新しい図書館はさまざまな使い方を想定して空間を構築しましたが、私たちが学生に期待しているのは想像もしなかったような使い方をしてくれること。学習において“想定外のできごと”というのは、必要なことだと思います。ここでの体験が人から人へと自然に伝わって、学生たちの“何か”が変わること、学びの伝播がおきることに期待しています。

明治学院大学
国際学部 教授
図書館長 情報センター長 秋月 望 教授
明治学院大学 横浜校舎図書館
1985年、横浜キャンパス開設に伴いオープンし、30周年の2015年3月、横浜キャンパス向上計画により全面改修。1、2年生中心の図書館として約40万冊の蔵書を提供している。白金校舎図書館では約80万冊所蔵。
詳しくは▶http://www.meijigakuin.ac.jp/library/(2015年3月取材。所属や名称、掲載内容は取材当時のものです。)


