「公会計とは?」と聞かれたときに、具体的な内容までしっかり説明できる方は意外と少ないかもしれません。しかし、地方自治体の財務管理において、公会計の知識は欠かせません。特に、平成27年度以降に全ての地方自治体で整備が進められた新地方公会計制度の導入により、発生主義と複式簿記が取り入れられ、財務情報のさらなる透明性向上が進んできました。
この記事では、公会計の基本から、新地方公会計制度の特徴、導入方法、運用の課題まで詳しく解説します。特に、実務面でのポイントや成功事例にも触れながら、自治体職員や地方公会計について詳しく知りたい方が公会計の概要を適切に理解できるようになることを目的としています。
index
- 公会計とは何か?
- 公会計の目的
- 公会計と企業会計の違い
- 新地方公会計制度の概要と特徴
- 新地方公会計制度の背景
- 発生主義と複式簿記の導入
- 公会計情報の活用
- 新地方公会計制度のまとめ
- 公会計の推進における課題
- 公会計制度実務の課題
- 公会計実務運用のポイント
- 公会計に関する学習方法と地方公会計検定
- 公会計の学習方法
- 地方公会計検定
- まとめ:公会計の意義と今後の展望
公会計とは何か?

公会計とは何かを理解するには定義と目的、企業会計との違いを理解することが重要です。以下で詳しく解説します。
公会計の目的
公会計とは、地方自治体や国の財政を管理するための会計制度です。主に、公共の資金をどのように収支しているかを透明に示し、公共サービスの提供に必要な予算を効率的に運用することを目的としています。
公会計は、企業会計と異なり、営利目的ではなく、公共の利益を最優先に考えます。具体的には、税収や補助金などの収入をどのように使っているか、支出の内容や運営の状況を市民に明示することが求められます。この透明性の確保は、住民の信頼を得るために非常に重要です。
公会計と企業会計の違い
公会計と企業会計の最大の違いは、目的と運用方法にあります。企業会計は利益追求を目的としており、財務状況や利益を最大化するために運用されます。一方、公会計は公共の資金を管理し、住民の福祉や公共サービスの持続的な提供を最優先に考えています。公会計では、透明性や説明責任が重要視され、税収や支出がどのように使われているかを住民に報告することが求められます。また、公会計は営利目的ではなく、社会的な責任を担う点が企業会計と大きく異なります。これにより、自治体の信頼性を維持するための重要な仕組みとなっています。
新地方公会計制度の概要と特徴

地方自治体の財務管理は、近年大きく変化しています。特に、平成18年の総務省による「新地方公会計制度」の導入により、従来の現金主義による会計管理から、より正確な財務状況を把握できる発生主義・複式簿記の考え方が求められるようになりました。これにより、自治体の財務情報がより透明化され、適正な資産・負債管理が可能になっています。
ここでは、以下のポイントをそれぞれ解説します。
- 新地方公会計制度の背景
- 発生主義と複式簿記の導入
- 新制度の特徴
新地方公会計制度の背景
新地方公会計制度の導入は、地方自治体の財政運営の透明性と効率性を向上させるために行われました。従来の現金主義会計では、資産や負債の全体像を把握することが難しく、財政状況の正確な把握や将来の財政計画の策定に課題がありました。特に、夕張市の財政破綻を契機に、地方自治体の財政健全化が強く求められるようになり、発生主義会計と複式簿記の導入が進められました。この背景には、地方自治体が抱える財政問題の複雑化や、住民への説明責任の強化がありました。新制度の導入により、地方自治体は財政状況をより正確に把握し、適切な財政運営を行うことが求められています。
発生主義と複式簿記の導入
発生主義会計とは、現金の動きに関わらず、取引やイベントが発生した時点で会計処理を行う方法です。これにより、資産や負債、収益や費用を正確に把握することが可能となります。一方、複式簿記は、取引の原因と結果を両方記録する方法で、財務情報の信頼性と透明性を高めます。これらの導入は、現金主義・単式簿記を補完するものであり、とってかわるものではありません。発生主義会計では、例えば、固定資産の減価償却費や退職給付引当金など、現金の動きがない費用も計上されるため、財政状況の全体像を把握することができます。また、複式簿記は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成する際に不可欠な手法であり、財務情報の一貫性と正確性を確保します。
公会計情報の活用
新地方公会計制度に基づく財務書類は、地方自治体の財政運営において重要な役割を果たします。例えば、固定資産台帳の整備により、公共施設の老朽化状況や維持管理コストを把握し、効率的な資産管理が可能となります。また、財務書類を活用したセグメント分析により、事業別・施設別のコストを明確にし、政策評価や予算編成に役立てることができます。さらに、財務情報を基にした経年比較や類似団体間の比較を行うことで、財政運営の改善点を見つけ出し、より効果的な財政運営が可能となります。これにより、地方自治体は限られた財源を有効に活用し、住民サービスの質を向上させることができます。
新地方公会計制度のまとめ
新地方公会計制度は、発生主義会計と複式簿記を基盤とし、地方自治体の財務情報を包括的に把握するための仕組みです。具体的には、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4つの財務書類を作成し、これらを基に財政状況を総合的に評価します。貸借対照表は、資産と負債のバランスを示し、行政コスト計算書は、行政サービスにかかるコストと収益を対比します。資金収支計算書は、現金の流れを示し、純資産変動計算書は、純資産の変動を明らかにします。これらの財務書類を通じて、地方自治体は財政の健全化を図り、住民に対する説明責任を果たすことが求められます。
公会計の推進における課題
公会計制度の導入には多くのメリットがありますが、実務においては課題も少なくありません。特に、発生主義と複式簿記の導入には、自治体ごとに会計業務のフローに差異がある点などが、推進のハードルとなっています。ここでは、課題や運用時の注意点について解説します。
公会計制度実務の課題
新地方公会計制度の運用にあたっては、いくつかの実務的な課題が存在します。まず、財務書類の作成には高度な専門知識が必要であり、職員の研修やスキルアップが求められます。また、固定資産台帳の整備や更新には多大な労力と時間がかかるため、効率的な運用方法の確立が課題となります。さらに、財務情報の活用においては、データの正確性と一貫性を保つためのシステム整備が不可欠です。これらの課題を克服するためには、地方自治体間での情報共有やベストプラクティスの導入が重要です。また、外部専門家の活用や、IT技術を駆使した効率的なデータ管理システムの導入も検討すべきです。
公会計実務運用のポイント
公会計実務において重要なポイントは、まず財務書類の正確な作成と適時な更新です。固定資産台帳の整備や減価償却の適切な計上を行い、資産の実態を正確に把握することが求められます。また、財務情報を活用した分析や評価を行い、政策決定や予算編成に反映させることが重要です。さらに、住民や議会に対する説明責任を果たすため、財務情報の透明性を確保し、積極的な情報開示を行うことが求められます。具体的には、財務諸表の公表や、住民向けの説明会の開催、インターネットを活用した情報提供などが考えられます。これにより、住民の理解と信頼を得ることができ、地方自治体の財政運営の透明性が向上します。
公会計に関する学習方法と地方公会計検定

公会計に関する学習方法と地方公会計検定について解説します。それぞれのポイントを把握することで、公会計への理解が深まります。
公会計の学習方法
公会計の学習方法には、まず基本的な理論を学ぶことが重要です。公会計に関する書籍や総務省が公開している地方公会計マニュアルなどを利用して、制度や仕組みの基礎をしっかり理解しましょう。次に、実務に即した学習が求められます。実際の運用方法を学ぶために、自治大学校の研修や地方公共団体が提供するセミナーに参加することも有効です。
また、オンラインでのコースや講座を活用することも、忙しい方にとって効果的です。さらに、実際の会計システムやツールを使用して、具体的な操作方法を学ぶことも重要です。これらの学習方法を組み合わせて、公会計に関する知識を深めることができます。
地方公会計検定
公会計に関する知識や技能を証明する検定として、一般財団法人日本ビジネス技能検定協会が実施する「地方公会計検定」があります。この資格は、新地方公会計制度に基づいた財務書類、固定資産台帳の作成に必要な知識や能力を測定するもので、地方自治体の財政状況や事業の効率性を分析・評価し、またそれを基にした政策を推進する役割を果たします。公会計に関する専門知識を持つ人材へのニーズは高く、地方自治体職員のキャリアアップや、将来的に地方自治体への転職や就職を目指す人にとって有用な検定と言えます。
まとめ:公会計の意義と今後の展望
今後の地方公会計制度の展望としては、さらなる情報の精緻化と活用の促進が挙げられます。特に、デジタル技術の活用により、財務情報の収集・分析・報告が効率化されることが期待されます。また、地方自治体間での財務情報の比較やベンチマークが進むことで、より効果的な財政運営が可能となるでしょう。さらに、住民参加型の財政運営が進むことで、地方自治体の透明性と信頼性が一層高まることが期待されます。これにより、地方自治体は住民のニーズに応じた柔軟な財政運営を行い、持続可能な地域社会の実現に寄与することができます。今後も、地方公会計制度の改善と発展を通じて、地方自治体の財政運営の質を向上させる取り組みが求められます。
関連情報もご覧ください
財務会計システムと公会計システムが一体となった統合型財務会計システム「e-ActiveStaff財務会計」は、地方公会計制度の統一的な基準に準拠し、日々仕訳/期末一括仕訳のいずれの運用にも対応可能です。また請求書データの電子化やワークフローの活用により、ペーパーレス化や決裁の迅速化など、財務会計事務の生産性向上も実現します。
公会計の円滑な実務と、効果的な運用に向けて、「e-ActiveStaff財務会計」をぜひご活用ください。
財務会計システムと公会計システムが一体となった、統合型財務会計システム。計画、予算、決算、評価のプロセスを効率的にマネジメントし、行政経営を強力に支援します。
https://www.uchida.co.jp/localgovernment/products/inside/zaimu/
地方自治体をはじめとする公共団体の業務に特化した電子決裁システムです。
https://www.uchida.co.jp/localgovernment/products/inside/denshi/
従来型の基本構想、総合計画、実施計画だけでなく、「ローカル・マニフェスト」や「地域まちづくり計画」、「行財政改革アクションプラン」といった計画 との一体的な運用による行政経営を実現します。
https://www.uchida.co.jp/localgovernment/products/inside/gyosei-hyoka/

内田洋行自治体分野のコラム編集チームです。地方自治体・官公庁の職員の方向けにお役立ち情報や業界動向情報をご紹介します。
合わせて読みたい
-
 コラム
コラム電子決裁がもたらす内部事務DX!成功に向けた道筋とは
業務効率化と住民サービス向上のため、自治体の電子決裁が進んでいます。本記事では、電子決裁導入のメリットや導入時の課題、システム選定のポイントなどを解説します。
-
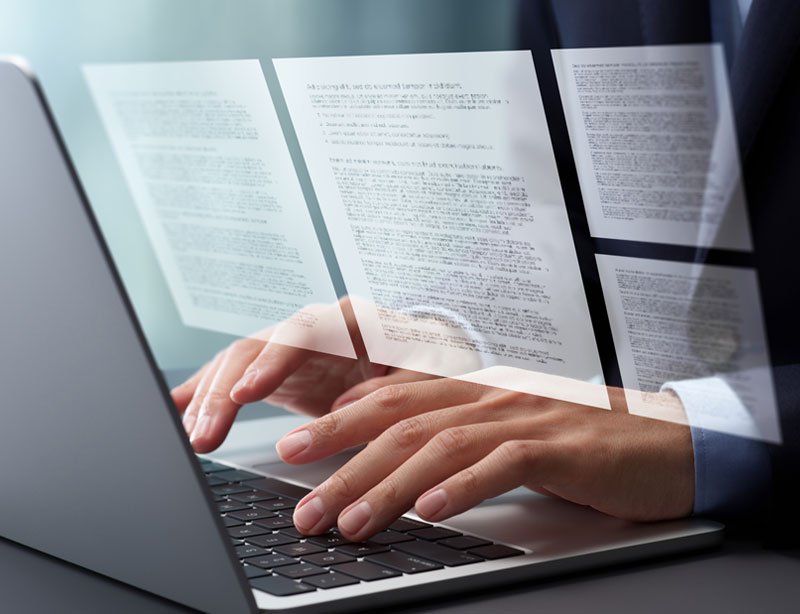 コラム
コラム文書管理システムとは?導入のメリットや選定のポイントを紹介
文書管理システムを導入したい自治体担当者に向けて、メリットや選び方を紹介します。
-
 イベントレポート
イベントレポート人が主人公となる“これから”の自治体DXを目指して 内田洋行「地方自治情報化推進フェア2024」出展レポート
10月9日と10日に幕張メッセで開催された「地方自治情報化推進フェア2024」における、内田洋行ブースの様子をご紹介します。





