
|
 |
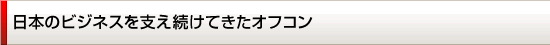
|
 |
 |
| オフコン(オフィスコンピュータ)は、主に中堅中小企業や大手企業の部門システムまたは地方自治体や計算機センターで「小型事務処理用計算機」として導入され、利用端末そのものも含み発展を遂げてきました。オフコンは、1980年代半ばからNEC9801シリーズで代表されるパソコンが飛躍的に市場に躍り出るまで、日本のビジネスを支えることとなります。 |
|
その後、こうしたパソコンを端末機として利用できるように、改良が加えられながらホストコンピュータとして「汎用機」「オフコン」へと位置づけが変わりました。さらには、米マイクロソフト社のWindowsが、1990年代から全世界的に浸透される「オープン化時代」に突入する荒波の中、TCP/IPという通信手段でネットワーク接続する、いわゆるLAN接続という「クライアント・サーバ型システム」時代が到来すると、その用途による種別として「オフコン」は、「ビジネスサーバ」つまり、ビジネスに欠かせない業務処理用コンピュータシステムとして称されるようになりました。そして現在もまだ尚、広く日本国内の企業や地方自治体で活用され続けているのです。
オフコンすなわち『オフィスコンピュータシステム』は、日本独自のコンピュータの歴史と共に、今も現役で活躍する極めてセキュリティポリシーの高いコンピュータシステムとして評価されています。 |
|
 |
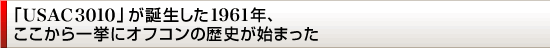
|
 |
それでは『オフコン』と呼ばれるコンピュータシステムが、誕生したのはいつの頃からでしょうか?
社団法人情報処理学会によると、「オフィスコンピュータ」と初めて命名したのは、1968年に当時の三菱電機が発売した「元帳会計計算機MELCO81」というコンピュータでした。
しかし、実際にはこの製品以前に、オフコンはすでに日本の国産技術により、わが国独自の発展形態を辿りながら国内の「小型事務用計算機」(直訳すると、スモールオフィスコンピュータ)市場を形成してきました。 |
| カシオ計算機からTUCコンピュライタ、日本電気からパラメトロン計算機NEAC1201が発売された1961年は、弊社が事務用品・教育関連の製品のほかに、新しくコンピュータシステム製品の販売サポートビジネスへ果敢に挑戦するきっかけとなった「USAC3010」というコンピュータが、当時まだ閑散としていた石川県能登半島の宇ノ気町のウノケ電子工業(現在の株式会社PFU)で誕生した年でもあります。 |
|
 |
| この年から一挙にオフコンの歴史が始まったと言っても過言ではありません。そして1974年に「特定電子工業及び特定電子工業振興臨時措置法」が制定され,それまでの超小型電子計算機と呼ばれてきた分類名称がオフィスコンピュータ(略してオフコン)に改められました。日本国として初めて正式な名称が誕生した瞬間です。 |
|
 |
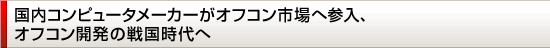
|
 |
 |
| 1970年、リコーが64ビット演算機「RICOM8」を発売し、1980年代には弊社と業務提携を行った富士通のベストセラー機「Kシリーズ」が誕生しました。日本電気、IBM、富士通「Kシリーズ」&内田洋行「USACシリーズ」連合、三菱電機、東芝など主要な国内外のコンピュータメーカーがオフコン市場に次々と参入し、切磋琢磨しながら日本独自のオフコン分野を形成してきました。まさに1980年代はオフコン開発の戦国時代でした。 |
|
| どの業界よりも早く「提案型営業」を求められ、「企業の成長支援システム」として営業マンとシステムエンジニアが力を合わせてお客様に最適なシステム提供することだけが、熾烈な競争に勝ち抜くための条件でした。各メーカー同士の開発競争の中で生まれたハードウエア技術やOS技術そして数々の業種・業務アプリケーションが、全国の中堅・中小企業のお客様の業務を支え続けてきました。 |
|
 |
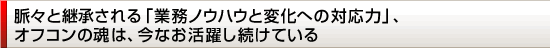
|
 |
脈々と継承される業務ノウハウと変化への対応力…、これこそがオフコン誕生から現在までお客様に支持されるシステム構築を可能にしている力なのです。
オープンシステムアーキテクチャが主流の現在でもなお、 『オフィスコンピュータシステム』が力強く生き続けているのは、本当にお客様のことを考え、縁の下の力となってお客様企業としての成長を支援し続ける魂が宿っているからです。もちろん、オフコン時代の様々なノウハウをオープンシステムと親和性の高い「業務アプリケーション」に継承し、広くその資産を還元している事実も忘れてはなりません。
『オフィスコンピュータシステム』の魂は、「ビジネスサーバ」に引き継がれ、また「業務アプリケーション」というソフトウエアに形を変えながらも生き続け、お客様をサポートする営業マンやシステムエンジニアのプロフェッショナリズムスピリットに宿り、今なお、お客様企業の成長を支援するシステムとして活躍を続けているのです。
|
|
 |
|
|
|
