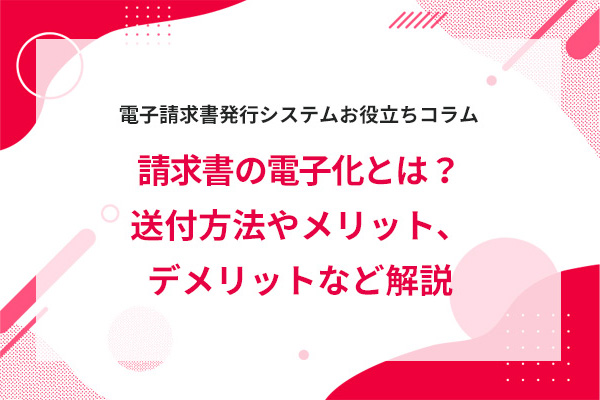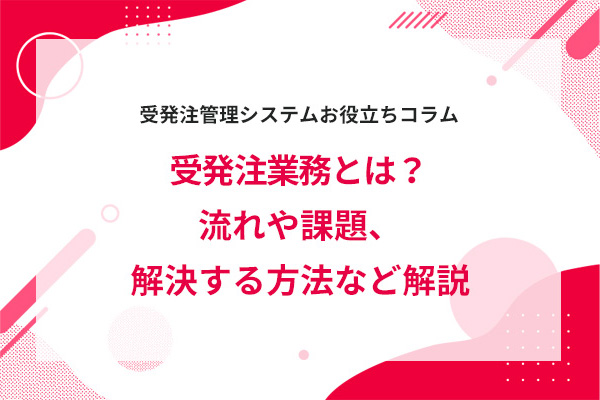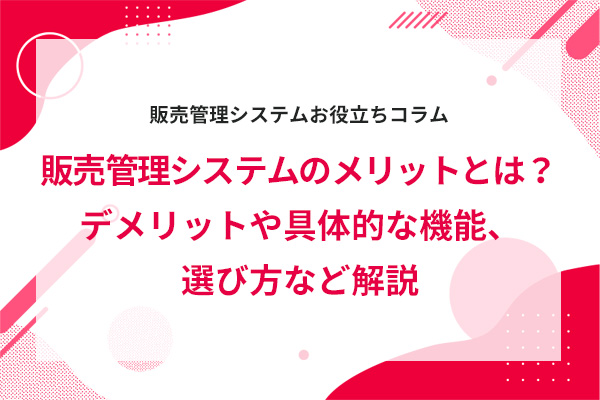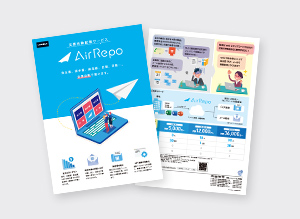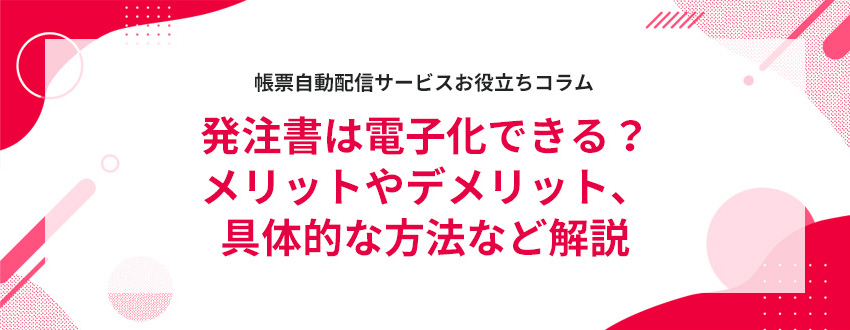
本記事では、発注書の電子化が進む背景や、そのメリットについて詳しく解説します。
1.発注書は電子化できる?
発注書の発行は、下請法の対象となる取引において義務付けられています(下請法第3条)。そのため、発注者は適切な形式で発注書を作成し、取引先に提供する必要があります。
また、2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、一定の条件を満たせば、従来の紙の発注書を電子データとして保存することが認められるようになりました。
ただし、発注書を電子データとして送受信した場合は、電子のまま保存することが義務付けられています。
※参考:どうすればいいの?「電子帳簿保存法」 | 経済産業省 中小企業庁サイト
発注書の電子化と保管が普及している背景
発注書の電子化やデータ保管が広がっている背景には、テレワークの拡大によるペーパーレス化の進展があります。特に、従来の紙ベースの管理では、発注書の確認や保管に多くの手間がかかるため、業務効率を向上させる手段としてデジタル化が求められるようになりました。
また、コロナ禍以降、テレワークやハイブリッドワークの導入が加速し、社外からでも業務を行える環境整備の必要性が高まったことも、電子化が進む大きな要因です。
2.電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(通称「電帳法」)は、会計ソフトで作成した帳簿データや、紙の請求書をスキャナーなどで読み取って電子保存する方法を定めた法律です。
また、取引先とデータでやりとりした請求書や領収書の保存方法も電帳法の対象となっており、電子取引によって受け取った書類は、一定の要件を満たした形で電子保存することが求められます。
3.発注書の保存期間
法人の場合、発注書や注文書は税法により、確定申告書の提出期限翌日から7年間の保存が義務付けられています。税務調査の際に必要な証拠書類として活用されるためであり、適切に保管しておくことが求められます。
また、欠損金の繰越控除を適用する場合は、保存期間が10年に延長されるため、より長期間の保管が必要になります。

4.発注書を電子化する方法
発注書を電子化する方法には、スキャンによるデータ化、Word や Excel の活用など、さまざまな方法があります。以下で詳しく解説します。
1)スキャンしてデータ化する
発注書の電子化方法の一つとして、スキャナーを使って紙の書類をデータ化する方法があります。
従来は、スキャン後3日以内にタイムスタンプを付与することが義務付けられていましたが、電子帳簿保存法の改正により、付与期間が延長され、自署が不要となりました。また、変更履歴が残るシステムを利用する場合には、タイムスタンプの付与も不要と定められています。
2)Word・Excel などを利用する
発注書は、Word や Excel、Googleドキュメントやスプレッドシートなどを活用して作成することも可能です。
専用ツールの導入が難しい場合や、個別要件があり全社共通システムでの運用が難しい場合などは、コスト面のメリットや管理が煩雑になるデメリットも考慮しながら、Word や Excel での作成を検討するとよいでしょう。
3)電子化ツールを活用する
電子化ツールを導入すると、タイムスタンプ機能を備えたものもあり、書類の改ざん防止が可能になります。セキュリティ面を強化したい企業にとっては、安心して発注書を管理できる手段となります。
特に、WordやExcelで作成した発注書は、保存や管理の仕組みを整えないと、データの改ざんや紛失のリスクが高まります。そうしたリスクを避けるためにも、電子化ツールの導入を検討するとよいでしょう。
4)購買システムから発行した発注書をPDFで保管する
電子帳簿保存法やインボイス制度などの各種法規制に対応した購買システムを活用すれば、発注書の電子化がよりスムーズに進められます。
システムを利用することで、発注書の発行から保存までを一元管理でき、法令に準拠した適切なデータ管理が可能になります。
▽関連ソリューションもご覧ください
電子帳簿保存法に対応した帳票保管が可能。スーパーカクテルCore販売はこちら
5.発注書を電子化するメリット
発注書を電子化することで、業務の効率化やコスト削減、安全なデータ管理が可能になります。以下で具体的なメリットについて解説します。
▼発注書の電子化によるメリットをご紹介した導入事例(水産流通様)
取引先へのスムーズな情報発信のため「エアレポ」を活用
1)発行当日に受け渡しができる
紙の発注書は、郵送に時間がかかるため、相手に届くまでに数日を要することが一般的です。しかし、電子化すれば、発行当日にメールで送信できるため、迅速な受け渡しが可能になります。
また、電子データ化することで、記載内容の確認や修正が簡単になり、情報のやり取りがスムーズになります。
2)保管や発送の費用削減に繋がる
紙の発注書は、誤記や修正が必要になった場合、再発行を行い、再度郵送する手間がかかります。修正や発送にはコストと時間がかかるため、業務負担の増加につながります。
一方で、発注書をスキャンして電子データ化すれば、紙の保管スペースを削減できるだけでなく、発送にかかる費用を削減できます。
3)ミスの削減と業務効率の向上が期待できる
発注書を電子データ化することで、印刷や郵送、ファイリング作業が不要になります。
また、受領側にとっても、紙の発注書を手入力で管理する場合、データ入力時にミスが発生しやすくなりますが、電子データであればツールを使った電子化がしやすくなり、入力作業の負担を軽減し、ヒューマンエラーを削減することができます。
▼発注書の電子化で業務を改善した導入事例(ナゴミヤ様)
「エアレポ」を活用し、お客様へ提案活動ができる時間を創出
4)安全に管理できる
紙の発注書は、紛失や破棄、経年劣化や汚損のリスクがあり、保管環境によっては適切に管理することが難しい場合もあります。しかし、電子データ化することで、これらのリスクを回避し、長期間にわたって安全に保管できます。
さらに、電子データは閲覧制限やパスワード設定を行うことで、必要な担当者のみがアクセスできる仕組みを構築できます。
5)リモートワークでも発行できる
発注書を電子化することで、押印や発送準備が不要となり、リモートワークでも発行できるようになります。
また、電子データはクラウド上に保存することもできるため、どこからでもアクセスが可能になり、発注書の管理がよりスムーズになります。
6.発注書を電子化するデメリット
発注書の電子化には多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。以下で詳しく解説します。
1)対象が多いと手間が増大する
紙媒体をスキャンして電子化する場合、1枚ずつの作業負担は小さいものの、発注書の量が多い場合は手間が増大する傾向があります。
単にスキャナーでデータ化するだけでなく、ファイル名の整備やフォルダ整理などの作業も必要となるため、大量の書類を管理する企業では導入時の負担が大きくなる可能性があります。
2)メモを書き込めない
スキャンした発注書は、主に「画像データ」として保存されるため、紙の書類のように手軽にメモを書き込むことができません。
こうした課題に対応するためには、電子化したデータに注釈を加えられるツールの活用や、メモを別のデータとして管理する方法を検討することが求められます。また、そもそもメモの必要性を減らすようなワークフローの改善も重要になります。
7.発注書を電子化する際の注意点
発注書の電子化を進める際には、適切な管理体制を整えることが重要です。以下で詳しく解説します。
1)「日付・金額・取引先」で検索しやすくする
電子帳簿保存法では、電子化した書類を「日付・金額・取引先」で検索できることが必須要件とされています。そのため、発注書を電子化する際には、スムーズに検索できる仕組みを整えることが求められます。
対策として、ファイル名に日付・金額・取引先を含めて保存する方法や、索引簿を作成して管理する方法があります。
2)不正・改ざん防止対策をしっかりと行う
電子帳簿保存法では、不正や改ざんを防ぐために、タイムスタンプの付与や、変更履歴が残るシステムの利用が求められています。
不正が発覚した場合には、重加算税が課される可能性もあるため、社内のルールを明確に定め、従業員への教育を徹底することが重要です。
3)セキュリティ対策も行う
発注書は長期間の保管が義務付けられているため、データの消失や紛失を防ぐためのセキュリティ対策が不可欠です。万が一、データが破損した場合や、不正アクセスによって情報が漏洩した場合、企業にとって大きなリスクとなります。
電子化を進める前からセキュリティ対策を意識し、クラウドストレージの選定時に適切な対策を検討することが重要です。
8.まとめ
発注書の電子化は、発行や保管の手間を削減し、業務の効率化やコスト削減につながる手段として、多くの企業で導入が進んでいます。特に、発行当日の受け渡しが可能になることや、リモートワークにも対応できる点は、紙の発注書にはない大きなメリットです。
内田洋行は、食品業・化学品業のほか、さまざまな業種に対応できるシステム導入実績を持ち、多岐にわたるプロセスを一元管理できる製販一体型統合パッケージ「スーパーカクテルシリーズ」を提供しています。また、発注書・納品書・請求書をはじめとする帳票を取引先に自動配信するクラウドサービス「エアレポ」は、スーパーカクテルとの連携が可能です。発注業務の効率化をご検討の方は是非、内田洋行にご相談ください。
関連記事
お役立ち資料