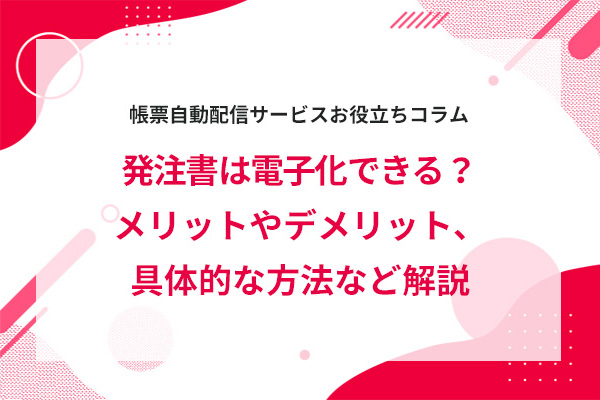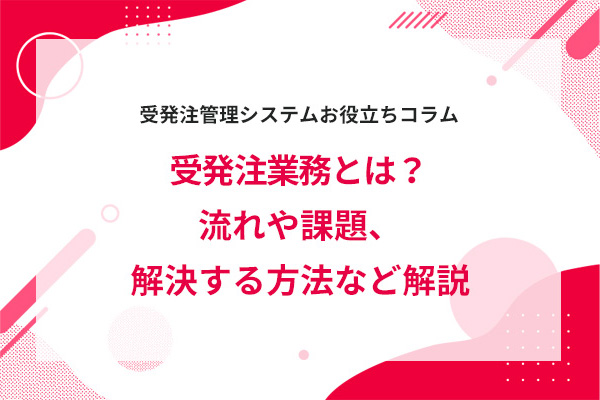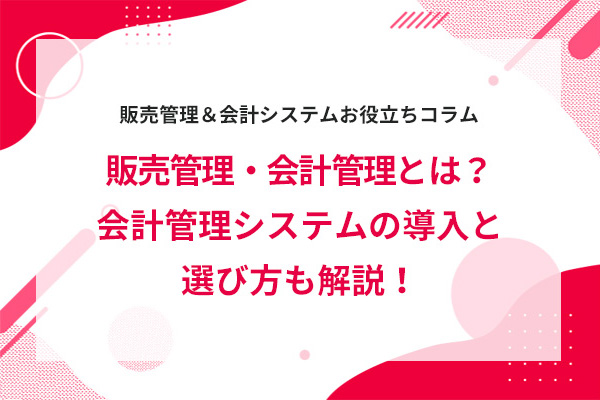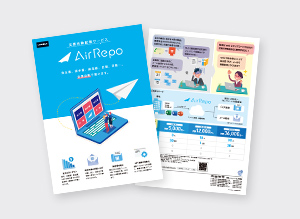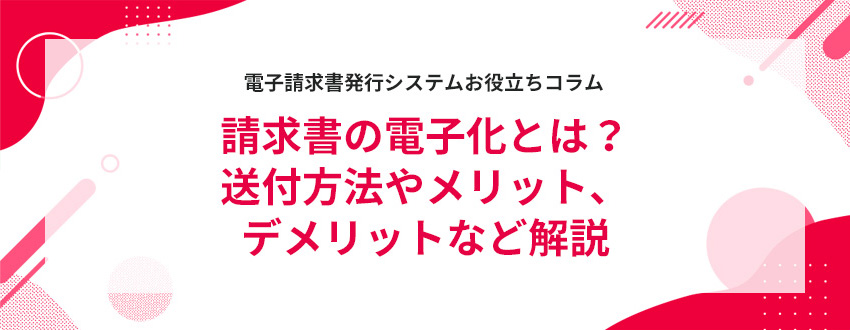
本記事では、請求書を電子化することで得られるメリットや、電子保存を行う際のポイントについて詳しく解説します。
1.請求書の電子化とは
請求書の電子化とは、PDFなどのデータ形式で請求書を電子的にやり取りすることを指します。
電子請求書の形式としては、WordやExcelなどのファイル形式も考えられますが、改ざんが容易であるため、多くの場合はPDF形式が用いられます。なお、電子請求書は紙の請求書と同じ法的効力を持つため、紙に印刷して郵送する必要はありません。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、税務関係書類(帳簿や請求書、領収書など)を電子データとして保存することを認めた法律です。
従来、税務関係書類は紙での保存が義務付けられていましたが、この法律の適用により、一定の要件を満たせば電子データでの保存が可能になりました。
2.電子化した請求書の送付方法
電子化した請求書の送付方法には、メール添付、Web上へのアップロード、専用システムを利用する方法があります。以下で詳しく解説します。

1)メールに添付して送付する
現在でも、電子請求書をメールに添付して送付するケースが多く、手軽に送信できる点がメリットです。しかし、複数の宛先に送る際は、誤送信のリスクがあるため、宛先の確認や送信前のチェックが重要になります。
また、ファイルサイズが大きすぎると送信できない場合があるため、圧縮やオンラインストレージの併用を検討する必要があります。
2)Web上にアップロードする
請求書をWebの共有クラウドストレージにアップロードし、そのURLを共有する方法もあります。添付と異なりメールボックスの容量を圧迫しないほか、URLに有効期限をつけることでセキュリティも向上します。
ただし、クラウドストレージの利用には注意点もあります。保存期間や保存容量がコストに比例する場合が多く、短期的な送付には向いていますが、長期保管には適していない場合があります。
3)システム経由で送付する
請求書作成・送付システムを利用する方法もあります。システムを導入することで、請求書の作成から送付までを自動化し、業務の負担を軽減できます。
また、登録済みの送付先を選択することで誤送付のリスクを低減できる点もメリットです。さらに、作成や送信のログを一元管理できるため、検索や修正、再発行も簡単に行うことができます。
3.請求書の電子化が進んでいる理由
請求書の電子化が進んでいる3つの理由について解説します。
1)電子帳簿保存法に対応するため
2022年1月の改正電子帳簿保存法により、電子データで受領した請求書は、紙に印刷せず電子データのまま保存することが義務付けられました。
また、今後は取引先から電子請求書を求められるケースが増えると考えられるため、請求書の発行や受領を電子化することで、スムーズな対応が可能になります。
2)環境問題に配慮するため
請求書を電子化することで、紙の使用機会が減り、印刷や郵送にかかる経費削減だけでなく、環境負荷の軽減にもつながります。
近年のSDGsへの関心の高まりを受け、電子化は持続可能な社会づくりへの取り組みの一環としても注目されています。
3)経理作業を効率化するため
電子化された請求書は、メールやクラウド経由で送受信できるため、印刷や封筒の準備、郵送作業が不要になります。
また、電子化された請求書であれば自動で管理・保存ができるため、経理業務の効率化につながります。業務負担を減らし、コスト削減やミスの防止を実現する手段として、請求書の電子化は有効な選択肢といえるでしょう。
4.請求書を電子化するメリット
請求書の電子化には、送付する側・受領する側の双方に多くのメリットがあります。以下で詳しく解説します。
1)請求書を送付する側のメリット
請求書を電子化すると、印刷や封入、郵送作業が不要になり、請求書発行にかかる手間と時間を大幅に削減できます。また、紙の請求書では用紙やインク、封筒、郵送費用が発生しますが、電子化することでこうしたコストを削減できます。
さらに、電子データとして一元管理できるため、請求書のファイリング作業や物理的な保管スペースが不要になります。
2)請求書を受領する側のメリット
請求書を電子データで受け取ることで、ファイル検索が容易になり、紙の請求書のようにファイリングしたものを捲って探す手間が不要になるほか、紛失や劣化のリスクを防ぐことができます。
また、受領した電子請求書をデータ化することで、手作業でのデータ入力が不要になり、作業時間と人為的ミスを削減できます。
さらに、電子データは送付後すぐに受け取ることができるため、請求書の処理スピードが向上し、業務の進行がスムーズになります。
5.請求書を電子化するデメリット
請求書の電子化には多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットもあります。以下で解説します。
1)保存していたデータが消える可能性がある
請求書を電子データとして管理する場合、ペーパーレス化による利便性が向上する一方で、データ消失のリスクが伴います。
そのため、多くの企業ではバックアップの実施やクラウドサービスの活用を行い、万が一の障害に備えています。
2)業務フローの再構築が必要になる
請求書の発行方法が従来の紙ベースから電子化に移行すると、業務フローを見直し、新たな仕組みを構築する必要があります。
また、電子請求書に対応するために、経理担当者や取引先への周知、新しい業務に対応したマニュアルの策定も必要です。
3)誤送信防止などのセキュリティ対策が必要になる
請求書には取引情報や金額などの機密性の高いデータが含まれているため、誤送信や情報漏洩を防ぐセキュリティ対策が不可欠です。
また、クラウドサービスを利用して電子請求書をやり取りする場合は、事前に取引先ごとに適切な送信先を設定する、アクセス権限を管理するなどの対策を講じることが重要です。
6.請求書を電子化する際の注意点
以下で、請求書を電子化する際の注意点について解説します。
1)取引先の同意を得る
電子請求書への移行を検討する際には、事前に告知を行い、PDF請求書でのやり取りについて了承を得ることが大切です。
また、一部の取引先では紙の請求書管理が必要な場合があるため、一方的に電子化を進めるのではなく、取引先ごとに対応可能か、紙を残す場合のフローについても整理しておくことが重要です。
2)今の業務フローに対応できるか確認する
電子請求書システムを導入する際は、現在の業務フローと適合するかを確認することが重要です。
特に、請求書の送付前に担当者の確認や承認フローがある場合、導入するシステムがそれに対応していないと、業務の負担が増えたり、確認ミスが発生したりするリスクがあります。
3)電子帳簿保存法の要件を満たす
電子請求書を発行する場合、PDF化した請求書は電子取引に該当するため、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
具体的には、請求書送付前にタイムスタンプを付与する、検索機能を確保するなど、電子帳簿保存法のルールに則った対応を行うことが求められます。
7.業務効率化を図るなら、電子請求書発行・送付システムを導入しよう
電子請求書発行システムを導入することで、請求書の作成や印刷の自動化が可能となります。印刷、封入、郵送などの請求書発行業務、問い合わせ対応や再発行にかかる工数を削減し、業務の効率化を実現できます。
また、送信を自動化することで、宛先の入力ミスや送付漏れといった人的ミスを防ぐことができます。
8.電子請求書発行システムの選び方
電子請求書発行システムの選び方について解説します。
1)自社の課題に合ったシステムを選ぶ
電子請求書発行システムにはさまざまな機能があり、システムによって対応範囲が異なります。そのため、導入時には自社が抱える課題を解決できるシステムかどうかを確認することが重要です。
例えば、請求書の作成や送付の自動化を目的とするのか、受領データの一元管理を重視するのかによって、必要な機能は異なります。
2)セキュリティ・信頼性を確認する
電子請求書発行システムは、請求書という機密情報を扱うため、提供元企業の信頼性も重要なポイントです。
システムの品質管理やセキュリティ対策はもちろん、長期間にわたって安定した運用が期待できるかどうか、企業情報を確認しましょう。
3)誰でも操作しやすいシステムを選ぶ
電子請求書発行システムを選ぶ際は、操作の簡単さも重要なポイントです。機能が充実していても、操作が複雑だと業務効率化につながらず、従業員が使いこなせない可能性があります。
そのため、直感的に操作できるシステムを選ぶことが大切です。また、一部機能を受信企業に使ってもらうシステムを採用する場合は、問い合わせを受ける可能性も考慮し、マニュアルの分かりやすさも確認しておきましょう。
9.まとめ
請求書の電子化は、業務の効率化、コスト削減、セキュリティ強化など、企業にとって多くのメリットをもたらします。
一方で、データの消失リスクや、業務フローの見直しが必要になるといったデメリットもあるため、事前の準備が重要です。電子化を成功させるには、取引先との調整を行い、自社の業務フローに適した電子請求書システムを選ぶことが大切です。
内田洋行は、食品業・化学品業の他、さまざまな業種に対応できるシステム導入実績を持ち、多岐にわたるプロセスを一元管理できる基幹業務システム(スーパーカクテルシリーズ)を提供しています。請求書や納品書などの受領文書の保管を標準機能として備え、更に送信についても、自動配信サービス「エアレポ」と連携することで、請求書作成から送付までをワンクリックで行うことが可能です。是非詳細お問い合わせください。
関連記事
お役立ち資料