- 企業情報
- 株主・投資家の皆様へ
- 商品・サービス
- サポート情報
- 採用情報
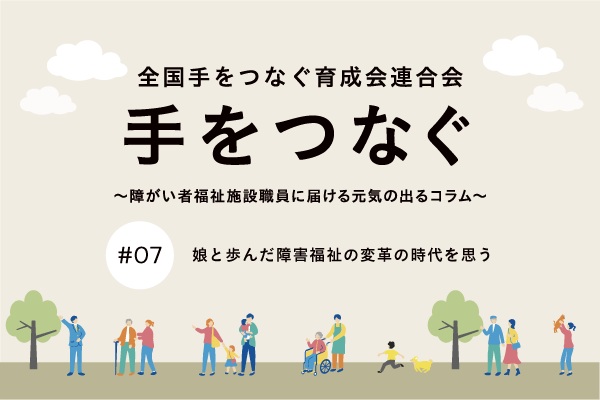
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 副会長 |
コラムをご愛読の皆さま、こんにちは。
今月は、自身も知的障がいの娘さんをもつ、全国手をつなぐ育成会連合会副会長による手記のご紹介です。小学校から高校までの学校生活や登下校の思い出とともに、障害福祉制度の変遷を振り返ります。ぜひ、福祉施設の経営者や職員の皆さまにとって、日々の施設運営や障がいのある方々へのサービス提供における励みとなれば幸いです。
このお話は、知的障害と自閉症を重複する34歳になる娘の子どもの頃のことです。今でこそ知的障害と言われていますが、児童通園施設や小学校低学年までは精神薄弱児と言われていました。行政用語とは言え親にとっては厳しい言葉でした。また、自閉傾向と言われていましたので特殊学級も情緒学級を進められました。当時は市内に64校ある小学校に情緒学級が設置されているところは4校しかありませんでした。その状況が示すように、まだ自閉症という障害が世間に知られていないころでした。よって情緒学級の教育も専門的とは言えないものだったように思いました。
しかし、子どもたちは通常級との交流をしながら 成長して6年間を過ごしました。 その間に3年生の時に忌まわしい精神薄弱児という言い方が、知的障害となり情緒学級が自閉・情緒学級となりました。そしてその間に自閉症への理解・対応も進んだように思いました。うれしかったのは、名前を言われてもそっぽを向いている我が子にどんなところにいても名前を呼んで仲間にいれてくれる通常級の子たちがいたことでした。 触れ合って過ごすうちに自閉症の子の特性を理解できたのですね、卒業式の時に気づき後悔したことがありました。それは6年間我が子の通学路が学校の駐車場から教室までだったことでした。可能な範囲で集団登校をさせていれば少しは外の環境にも触れられたのにと思いました。
平成15年、それまでの障害福祉が措置制度から契約制度になった年に、娘は養護学校の中学部に進級しました。そして長い夏休みが終わり2学期になった時の出来事です。突然担任から「通学をスクールバスではなく路線バスにしましょう。」と言われました。小学校の6年間は、親の車が移動手段でしたので家族も路線バスに乗った経験がほとんどありませんでした。担任から「路線バス通学の練習をしましょう」と言われ、早速、母親は仕事を一時やめて娘と一緒に路線バス通学の訓練を始めました。自宅近くのバス停で6時50分に乗車、駅で乗換えて養護学校まで約1時間30分の所要時間です。実は、路線バス利用は、娘は初めてですが親も車ばかりですので料金の支払いなど戸惑いました。親子での朝夕の登下校一日二往復が始まりました。このパターンは1週間半ほどで済みましたが、家の前のバス停から乗り換えの駅までは1か月半続きました。親子訓練は、母親ばかりでなく父親の私も経験しましたが、いつも座る場所が空いていないときのしぐさや、自分の降りるバス停の前から降車ボタンを押す準備をしたり、いろいろなこだわりが見られました。
母親とのバス通学の練習は、当初は高等部卒業まで続くと思っていましたが、一カ月半ほどで、一人で通うことができるようになりました。自閉症という特性でしょうか決まったことは間違いなくやることができるようになりました。そして、一人でバスに乗る日の出来事です。いつも通勤通学で一緒になるお客さんは朝早いので眠っているようでしたが、その日ばかりはバス停で見送る母親をみんなで「お母さん大丈夫!」という眼差しで見たそうです。母親はいつものバスのお客さんは娘のことを気にしてくれていたと思いました。そして、バスに向かって「娘をお願いします」とお辞儀をしました。
高等部になった4月、朝のバスに乗るのを嫌がるようになりました。どうしてかなとバスに乗ってみると、いつも乗る6時50分のバス路線が変更となり小学1年生がたくさん乗っていました。その小学生のお喋りが娘には不快音になったのです。運転手や上級生がバスの中では静かにと言ってもおさまりません。娘は朝の路線バス通学は出来なくなり、母親に学校まで送ってもらうようになりました。その時、バスや電車の中では、大きな声や携帯電話はマナーモードにして人の迷惑にならないようにと言っていることの意味がよく理解できました。
娘が高等部になった年は、平成18年で障害福祉が障害者自立支援法となり、発達障害も含む精神障害も制度に含まれるようになりました。生まれた時は精神薄弱と言われ支援サービスが殆どありませんでしたが、学校にいる間に障害福祉が大きく変わった12年間であったとつくづく思います。私たち知的障害者は多くの支援に支えられて地域生活をおくっています。これからもよろしくお願いします。
▽福祉業界の方向けに、新着コラムやITの最新動向など、お役立ち情報をメールでお届けします!
登録は無料ですので、お気軽にお申し込みください
関連記事
障がい者福祉施設の経営者・職員の皆さまへ