- 企業情報
- 株主・投資家の皆様へ
- 商品・サービス
- サポート情報
- 採用情報
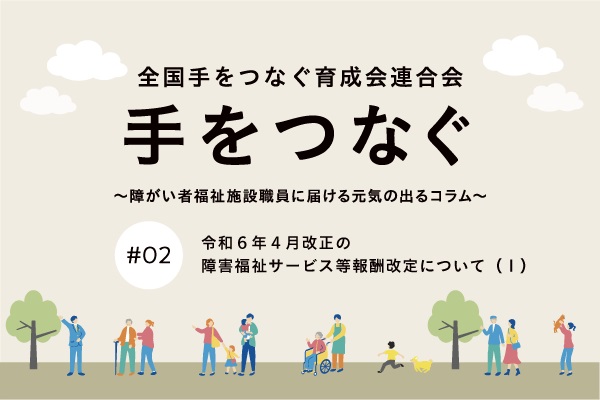
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 |
コラムをご愛読の皆さま、こんにちは。
私は(一社)全国手をつなぐ育成会連合会(以下「本会」という。)の常務理事兼事務局長 又村あおい と申します。全育連の事務局業務のほか、主に知的・発達障害領域の施策に関する政策提言や要望活動を担当しています。
今年の4月から、障害者総合支援法と児童福祉法の改正が施行され、あわせて障害児者福祉サービスの報酬が改定されました。今回の報酬改定では、知的・発達障害のある人や子ども(以下、知的障害者)への直接的な影響が見込まれる分野が多数あります。障害福祉サービス事業所の運営にも影響が大きい部分を中心に、今回と次回でご紹介いたします。
本題へ入る前に、そもそも「報酬改定」とは何か、簡単に把握しておきましょう。知的障害者が利用する各種の福祉サービスは、提供した支援(サービス)に応じた「報酬」が設定されています。たとえば、家事を手伝うヘルパー(家事援助)を1時間提供すると、報酬は約2,400円となります。通常はこのうち1割が利用者負担となりますが、収入の中心が障害基礎年金(住民税が非課税)となっている知的障害者の場合には、利用者負担が免除されています。
このように、国が定めるさまざまなサービスを提供すると「基本報酬」が支払われ、たとえば専門職が配置されていたり、より手厚い職員配置だったりすると各種の「加算」が上乗せされる仕組みになっています。ほとんどのサービスは基本報酬だけで運営することが難しく、事業所側としてはできるだけ加算を算定できるように工夫することとなりますが、加算に関しては国が政策的に強化したい分野に重点配分されていることが多く、このことが知的障害者の暮らしぶりに影響するわけです。報酬改定の細かい内容に関心のある方は、特に加算の部分へ注目してみると国が重視する方向性が見えてくると思います。
以下、今回の法改正、報酬改定において知的障害者への影響が予想される分野を重点的にご紹介します。あわせて、最新の障害福祉サービス一覧もご参照ください。
参考資料:障害児・者福祉サービス一覧(PDF)ダウンロード
通所サービスにおける昼食費用を軽減する食事提供体制加算については、今回の報酬改定議論で存廃が議論されていましたが、最終的には存続となりました。したがって、利用者側としては「今までどおり(食事提供体制加算の対象施設であれば、食材料費相当額で食事を食べられる)」ということになりますが、事業所側からみると話は大きく変わります。
加算の趣旨が大幅に見直され、いわば「食を通じた健康増進加算」といった位置づけとなりました。具体的には、栄養士が献立作成に関わる、適量食べているかを確認する、定期的に体重測定を行うといった取組みをすることで初めて食事提供体制加算が算定できる扱いに変更されています。利用者側としては、食費の軽減とあわせて健康づくりにも役立つ加算となりますので、評価できるといえるでしょう。
今回の報酬改定における隠れた重要ポイントが、意思決定支援の取組みとなります。
これまでも、障害福祉サービスや相談支援における意思決定支援は重要な取組みとされてきましたが、実際のサービス提供場面における実効性を担保する仕組みが十分とはいえませんでした。しかし、今回の報酬改定でサービス担当者会議、個別支援会議につき「原則本人同席」となったことは、大きな転換点となる可能性を秘めています。
サービス担当者会議とは相談支援専門員が開催する会議で、本人のサービス等利用計画に基づく支援を実施するために関係する福祉サービス事業所などが集まって協議する場です。個別支援会議とはサービス管理責任者が開催する会議で、サービス担当者会議などを経て、個々の事業所において提供する支援に関し、その方向性と具体的な内容を話し合う場です。つまり、今後はサービス利用の全体調整場面、個別のサービス利用場面の双方で本人の意向を確認することが原則となるわけです。
もちろん、「原則」ですので「例外」もありますが、たとえば医療的ケアが必要な人で感染症リスクが非常に高いケース、強度行動障害の状態にあって多人数がいる環境そのものがパニックのきっかけになってしまうケースのように、相当の理由がないと「例外」とはいえない運用となります。逆にいえば、重度知的障害であることは理由になりませんから、重度障害者であっても本人の状況に合わせて理解できるような資料を用意するなど、会議の持ち方に工夫する必要が出てくるでしょう。
▽福祉業界の方向けに、新着コラムやITの最新動向など、お役立ち情報をメールでお届けします!
登録は無料ですので、お気軽にお申し込みください
関連記事
障がい者福祉施設の経営者・職員の皆さまへ